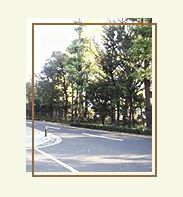|
3日目 東京の道
日本にきて3日目、朝9時にあの電話がまたしゃべりだしました。今度は私も堂々と受話器を取って、いつものとおり「ウェイ?」で応対しましたが、返答がないので「もしもし」ともう一度話したら、やっと相手が声を出しました。
相手は会館の管理人でした。私に事務室に入館手続きをするように知らせてくれたのです。事務室で手続きをしながら、管理人は昨日私あてに2回も電話をかけたのに、私がいなかったという話をしました。私は謝りながらも「あなただったのか!心臓が飛び出す寸前だったのに!」と、心中密かに思いました。
事務室を出て、そのまま学校へ向かいました。学校は会館からそれほど遠くありません。電車に乗り2つ先の駅で下りれば着くそうです。学校は駅からも近いということなので、見つけやすいだろうと私は思い込んでいました。万が一のため、一応地図を持ってはいきましたが。
駅についた私は、自信満々に地図で学校の位置を調べてから、そちらに足を運び出しました。が、暫くして方向を間違えたことに気づき、また後戻りして、もう一度やり直したのですが結果は同じでした。余りのことに、再び地図をよく分析してみたのですが、間違った原因を見つけ出せませんでした。
思い切って東京の地図を一冊買ってきて、それを学校から配られた地図と見比べてみると、学校の地図は単なる見取り図なので、方向ははっきり示しているものの、道はすべて直線で書かれてあるのだと気づきました。しかし目の前の道路は直線のものは一つもありません。
駅の出口が東口と西口というふうに分けられていても、暫く歩くと方向は変わってしまいます。また、周りを見回せば、町中で漢字の書かれている看板を見つけることができますが、いかに中国と似ている感じがしても、やはりここは北京ではなく、東京なのだということを悟りました。すっかりさっきの生意気を失ってしまった私は、まめに他人に尋ねながら学校にたどり着きました。
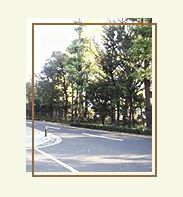
会館に帰ってくるともう午後になっていました。日用品を買いに、ついでに周りの環境も見ておこうと思って出かけました。私は昨日歩いた細い道に沿って歩いていきました。
暫くして新しく開業した米店を見かけました。入ってみると、中で売られている5キロ単位のお米の値段は会館前にあるお店のものより、なんと千円近くも安いことに気がついて、こりゃあ運がいいね!と心中喜びました。
早速2つ買って、2つのビニール袋を1つに繋いで肩の前後にぶら下げるように乗せて、米屋を出ました。
今の私の姿はまるで阿凡提(中国の昔話の主人公)みたいだね、驢馬が一匹あったらもっといいね、などといろいろ想像しながら会館に戻るべく歩き出しました。
やがて日が暮れました。早く会館に着かなくちゃと思い、あえて元の道ではなく近道だと思う方向を選びました。しかし歩くこと30分、まったく知っている景色が見えてきません。
私はすこし不安になりました。背負っているお米もさらに重くなったようです。東京は大都会なのに、夜になると住宅地はまるで墓地のように静かで、外には人影も見えません。
もう暫く歩くと、やっと明かりが見えてきました。それはいくつかのお店でした。しかし肝心な会館はなかなか見えてきません。
ついにイライラした私は、店から出てきた1人の中年女性に尋ねてみました。その答えは私が一番聞きたくない結果でした。10キロもの米を担いで、間違った方向に3つ先の駅まで歩いてきてしまったなんて!
その中年女性は途方に暮れた私の顔を見て、自ら駅まで連れていってくれるといい、重い米も彼女の自転車に乗せてもらいました。
10分後、駅に着きました。彼女は気をつけて帰ってくださいと言い残して帰りました。なんと優しい人でしょう。あの日本人女性の好意を忘れることはないでしょう。
その夜、私は来日後初めての手紙を書きました。内容はすべてこの3日間の出来事です。手紙を書き終わったら、あまりにいろいろな感慨が沸いてきたので、ふとある唐詩が心に湧いてきました。
洛陽城内に秋風を見ると、家書を作ろうと意が万叢あり、
復怱怱言い尽きずと恐れるや、行人に監られて又開封に発す。
注:
家書 手紙
意が万叢あり 言いたいことがいっぱいある
怱々 急いで
行人 犯人を押送する役人のこと
開封 中国河南省の地名
4日目
朝早く起きて、久しぶりにさっぱりした気分で、近所にちょっと散歩に出かけました。するとゴミ捨て場でまだ古くもないカラーテレビを見かけました。
日本に来る前に、日本人は使えるものも捨てると色々と聞きましたが、自分の目で見たのは初めてなので、やっぱりちょっとショックを受けました。近づいてみると、会館のロビーに並んだテレビよりも新しいものでした。
会館に戻るとき、ちょうど同じ会館に住んでいる人に会ったので、ついでにそのことを教えたのですが、その人はすぐに「コードが付いているか。」とまじめな顔で私に聞きました。コードが付いていると教えたら、向こうは「それじゃ使えるね。」とつぶやいて、そこに行くために場所を聞きました。さっぱりわからない表情をした私を見て、その人は「そのうちにわかるよ。」と言い捨てて、去ってしまいました。
朝ご飯を食べてから、やはり自分は見聞が狭いのではないかと思い、昔聞いた笑い話を思い出して、思わず笑みをもらしてしまいました。その笑い話はこんなものでした。
ある日、農家の主婦何人かが、井戸端で世間話をしていました。ある主婦は「こんな真夏の日に、皇后様はどうやって過ごしているのかしら」と仲間に聞きました。もう一人の主婦は「皇后様はね、私たちのように苦労はしないでしょうね。きっと布でできた蚊帳の中に寝て、ながーい、長い昼寝をしているでしょう。目が覚めたら、蚊帳から片手を出して、付き添いの宦官に『ねえ、干し柿を頂戴。』というのでしょう。」
この笑い話は見聞の狭い人を皮肉ったもので、農家の主婦はどんなに考えても皇后様の贅沢さが想像できないので、結局自分があこがれているものを皇后の生活として思い描くしかないということです。
以前は自分も見聞が広いほうだと思い込んでいたのですが、日本に来て初めて自分はまだ知ってることが少ないのだと認識してしまい、日本のゴミはその最初のきっかけではないかと思いました。
私の幼いころ、中国のゴミ捨て場にあった主なものは、石炭を燃やした後の灰でした。当時の家庭で使われていた燃料は、石炭の粉と粘土で出来た塊でした。それ以外には野菜のいらない部分だけでした。
この十数年間、ゴミの構成はだいぶ変わりました。一番大きく変わったのは、ガスの利用に伴い、石炭の灰がほとんど出なくなったことです。
食べる物の変化に従い生ゴミの量が急増し、使えない家具や服装や靴も見かけました。しかしそれは確かに使えないものばかりでした。
日本に長くいると、だんだんその仕組みが分かってくるものです。都市部では、ゴミの収集日の規定があり、テレビなどの家電製品は「粗大ゴミ」と分類されます。
その処理は手間がかかるため、それを捨てる人に処理費用が課されます。その課金から逃れるため、住んでいる地域以外のところに捨てる人もいるし、課金を払うつもりで指定場所に捨てた人でも、誰か欲しがる人がいないものかと思っているものです。
数十年前がどうだったか分かりませんが、今の日本人のゴミの捨て方はすごいものです。各種の家具、家電製品、洋服、布団、キッチン用品などすべてが揃っています。
特に引越しのときには、使用していた道具全てを丸ごと捨てて、全部買い換える人もいます。これらの物はほとんどまだ使えるもので、商標のシール、説明書、付属する備品まで付いている捨て方を見て、持ち主が普段使う時もかなり用心していたことさえ感じ取れるのです。
幼い頃から「新三年 旧三年 縫縫補補又三年(新品は3年、古着も3年、繕ってまた3年)」という生活に慣れた私は、小学校のテキストに載っていた「細水長流、吃穿不愁、一頓省一口、一年省幾斗(水は細ければ長く流れ、生活に困ることがない、一食に一口節約すれば、一年で多く貯まる)」という本文を暗誦したことがあり、「勤倹是我們的傳家宝、社会主義建設離不了(節約は家の宝で、社会主義建設には欠かすことができない)」という歌を歌ったこともありました。
また大人になってから「一茶一飯、当思来之不易,半絲半褸、恒念物力惟艱。(一茶一飯、得るのは容易くないと考えるべき、半端の生地でも作るのは難しいと思うべく)」という古い文章を読んだことがあります。
そんな私はとにかく「節約は美徳だ」と思います。 いつどこで読んだかわかりませんが、ある有名人が「先進国は後進国の鏡で、後進国の国民は自分の国が数十年後にどういう様子をしているか分からない場合は、先進国に行ってみればわかる」といっていました。
ただし私は日本に来ても、中国が日本のように発達したときの様子を想像できないのです。94年に冷害で米不足だった時期に、ある日本人の評論家は「日本人はまもなく機能の優れた家電製品に囲まれて餓死することでしょう」と書いていました。本当にそう考えるなら、私も捨ててもいいという気持ちになるでしょう。 上一页 [1] [2] 尾页
|